英語の発音で悩んでいませんか?
「どんなに頑張っても通じない」「ネイティブとの違いがわからない」
そんなお悩みを解決するため、今回は日本人が特に苦手とする重要な発音を徹底解説します。
1. リズムとアクセント
🎵 英語は「ストレス・タイミング」言語
日本語と違い、英語は重要な音節だけを強く発音し、他は弱く短く発音します。
たとえば、小さな子どもが何かを訴えるとき、
言いたいこと(=重要な部分)を大きな声で強く言うことがありますよね。
例: I WANT to EAT CAKE.
- 強: WANT, EAT, CAKE(内容語)
- 弱: I, to, to, the(機能語)
日本語(強弱なし)
「わたし は こうえん に いきたい」
→ すべての音節が均等なリズムで読まれる。
📍 単語のストレス位置
- 2音節の名詞・形容詞:多くは最初にストレス
- TEAcher(教師)
- HAPpy(幸せ)
- 2音節の動詞:多くは最後にストレス
- beGIN(始める)
- deCIDE(決める)
- 同じ単語でも品詞で変わる
- REcord(名詞:記録)/ reCORD(動詞:記録する)
- PREsent(名詞:贈り物)/ preSENT(動詞:贈呈する)
2. 英語の音の全体像
🔤 IPA(国際音声記号)の重要性
正確な発音習得には、IPA表記の理解が不可欠です。
日本語の「カタカナ表記」では限界があります。
🎼 英語の母音システム
単母音(12個)
ひとつの口の形で発音される、変化しない安定した母音です
- /iː/(seat), /ɪ/(sit), /e/(bed), /æ/(cat)
- /ɑː/(father), /ɒ/(lot), /ɔː/(law), /ʊ/(foot)
- /uː/(food), /ʌ/(cup), /ɜː/(bird), /ə/(about)
| 音 | 例単語 | 解説 |
|---|---|---|
| /iː/ | seat, see | 長い「イー」。口を横に引く。 |
| /ɪ/ | sit, bit | 短く弱めの「イ」。 |
| /e/ | bed, head | 日本語の「エ」に近いが少し広め。 |
| /æ/ | cat, man | 「ア」と「エ」の中間音。「エァ」に近い。 |
| /ɑː/ | father, car | 口を大きく開ける「アー」。 |
| /ɒ/ | lot, dog | 唇を丸くした「オ」。英英発音に多い。 |
| /ɔː/ | law, call | 長く深い「オー」。 |
| /ʊ/ | foot, book | 短く弱い「ウ」。口は少し丸める。 |
| /uː/ | food, blue | 長い「ウー」。しっかり唇を丸めて。 |
| /ʌ/ | cup, love | 日本語にない「ア」音。喉の奥で。 |
| /ɜː/ | bird, girl | 舌を巻かず、のど奥で出す「アー」風。 |
| /ə/ | about, sofa | シュワ音。弱く短い「ア」。脱力。 |
二重母音(8個)
ひとつの母音から別の母音へ、口の形が滑らかに変化する音
- /eɪ/(day), /aɪ/(my), /ɔɪ/(boy), /aʊ/(how)
- /əʊ/(go), /ɪə/(here), /eə/(hair), /ʊə/(sure)
| 音 | 例単語 | 解説 |
|---|---|---|
| /eɪ/ | day, say | 「エ」→「イ」。英語の「エイ」。 |
| /aɪ/ | my, try | 「ア」→「イ」。日本語の「アイ」に近い。 |
| /ɔɪ/ | boy, toy | 「オ」→「イ」。口を丸めて始める。 |
| /aʊ/ | how, now | 「ア」→「ウ」。驚いたときの「アウ!」。 |
| /əʊ/ | go, home | 「オ」→「ウ」。米音は/oʊ/に近い。 |
| /ɪə/ | here, idea | 「イ」→「ア」。やや曖昧な響き。 |
| /eə/ | hair, care | 「エ」→「ア」。英音に多い。 |
| /ʊə/ | sure, tour | 「ウ」→「ア」。口をすぼめて始める。 |
🎵 英語の子音システム
- 閉鎖音: /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/
- 摩擦音: /f/, /v/, /θ/, /ð/, /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /h/
- 破擦音: /tʃ/, /dʒ/
- 鼻音: /m/, /n/, /ŋ/
- 流音: /l/, /r/
- 半母音: /w/, /j/
閉鎖音
口の中で空気を完全に止めて、パッと破裂させる音。日本語の「ぱ・た・か」に近い。
| 音 | 発音例 | 解説 |
|---|---|---|
| /p/ | pen, map | 無声音。唇を閉じて「プッ」と破裂。 |
| /b/ | bed, cab | 有声音。/p/と同じだが声を出す。「ブッ」。 |
| /t/ | top, cat | 無声音。舌先を上前歯の裏に当てて「トッ」。 |
| /d/ | dog, mad | 有声音。「ドッ」。/t/に声をつけた音。 |
| /k/ | cat, back | 無声音。舌の奥で空気を止めて「クッ」。 |
| /g/ | go, bag | 有声音。「グッ」。/k/に声を加えた音。 |
摩擦音
口の中を細くして、空気をスーッとこすらせる音。
| 音 | 発音例 | 解説 |
|---|---|---|
| /f/ | fish, leaf | 上の歯を下唇に当てて「フ」。 |
| /v/ | van, save | /f/の有声音。「ヴ」。日本語にない。 |
| /θ/ | think, bath | 舌を歯に当てて「スィ」っぽく。 |
| /ð/ | this, mother | /θ/の有声音。「ズィ」。 |
| /s/ | sun, kiss | 「ス」。日本語と近い。 |
| /z/ | zoo, busy | 有声音の「ズ」。 |
| /ʃ/ | she, fish | 「シュ」。息が強め。 |
| /ʒ/ | measure, vision | 「ジュ」。日本語にないが大事。 |
| /h/ | hat, hope | 喉から息を出す「ハ」。 |
破擦音
閉鎖音+摩擦音が合体した音。
| 音 | 発音例 | 解説 |
|---|---|---|
| /tʃ/ | check, watch | 「チッ」。/t/と/ʃ/の連続。 |
| /dʒ/ | jump, edge | 「ヂュ」。/d/と/ʒ/の連続。 |
鼻音
鼻から空気を出す。日本語にもある音。
| 音 | 発音例 | 解説 |
|---|---|---|
| /m/ | man, lamp | 唇を閉じて鼻から「ム」。 |
| /n/ | no, ten | 舌を上につけて「ヌ」。 |
| /ŋ/ | sing, long | 「ング」。語尾で多い。 |
流音
空気の流れを軽く妨げながら出す音。
| 音 | 発音例 | 解説 |
|---|---|---|
| /l/ | light, bell | 舌先を歯の裏に軽く当てて「ル」。 |
| /r/ | red, car | 舌を丸めて「ゥラ」。どこにも触れない。 |
半母音
母音のように聞こえるが、子音として振る舞う音。
| 音 | 発音例 | 解説 |
|---|---|---|
| /w/ | win, cow | 「ウ」に近い。「ワ」と発音しないよう注意。 |
| /j/ | yes, yogurt | 「イ」に近い。「ヤ」ではなく「イェ」感覚。 |
3. 母音
日本人が最も苦手とする母音TOP5
1. [æ](cat)と[ʌ](cup)の違い
💡 Cat(ネコ)
- 発音: 「キャッ」じゃなく「ケァッ」
- 口の形: 顎をグッと下げて、口を横にしっかり開く
- 音質: 「ア」と「エ」の中間(”あえぐ猫”のイメージ)
- 特徴: 明るい音
💡 Cup(カップ)
- 発音: 「コップ」ではなく「カッ(喉から)」
- 口の形: 顎は軽く開く、あまり口を広げない
- 音質: 短く、深く「喉奥から出す”ア”」
- 特徴: 少しこもった音
🔥 比較のコツ: Cat = 「明るく叫ぶネコ」 Cup = 「お腹から出る”力の抜けたア”」
2. [iː](seat)と[ɪ](sit)の違い
💡 Seat(座席)
- 発音: 「スィート」よりも「スィーッ」
- 口の形: 口を横に思いっきり引いて「イーッ」
- 舌の位置: 舌を上前方にギリギリまで上げる
- 特徴: 緊張感あり(息止めながら笑う感じ)
💡 Sit(座る)
- 発音: 「スィッ(短く軽く)」
- 口の形: 口はあまり横に引かない
- 舌の位置: 舌はリラックスして少し低い位置
- 特徴: 力を抜いて「イ」と「エ」の中間っぽい
🔥 比較のコツ: Seat = 緊張してる「イ」 Sit = 力の抜けた「イ」
3. [uː](food)と[ʊ](foot)の違い
💡 Food(食べ物)
- 発音: 「フー(唇とがらせて長め)」
- 口の形: 口をしっかり丸める
- 舌の位置: 舌を後ろの上に引く
- 特徴: 息を長く出す
💡 Foot(足)
- 発音: 「フッ(短く軽く)」
- 口の形: 口はやや丸めるが軽め
- 舌の位置: 舌の位置はfoodより前寄り
- 特徴: 短く、こもったような音
🔥 比較のコツ: Food = 美味しそうに伸ばす「ウー」 Foot = 軽く踏んづけるように「ウッ」
4. [ɔː](law)と[ɑ](lot)の違い
💡 Law(法律)
- 発音: 「ロー(口縦に開けて丸める)」
- 口の形: 口を縦に大きく開く
- 唇の形: 唇を丸めて前に出す
- 特徴: 深く、長く響かせる
💡 Lot(たくさん)
- 発音: 「ラット」ではなく「ロット(喉奥から)」
- 口の形: 口を縦に大きく開く
- 唇の形: 唇は丸めない
- 特徴: あくび直前のような喉奥の音
🔥 比較のコツ: Law = 「オーーー」と唇丸める Lot = 「アーーー」と喉奥から
5. [ər](bird)と[ɜː](nurse)- R音性母音
💡 Bird(鳥)
- 発音: 「バード」じゃなく「バーゥド」
- 舌の位置: 舌を後ろに引いて丸める
- 注意点: 舌先をどこにも触れさせない
- 音質: 「ア」と「ウ」の中間に「ル」が混ざった音
💡 Nurse(看護師)
- 発音: 「ナース」ではなく「ナーゥス」
- 舌の位置: 同じく舌を後ろに引く
- 特徴: より長く、深く響かせる
- 音質: 「アー」の中に「ル」が混ざる感覚
🔥 発音のコツ: 舌を奥に引っ込めて「ル」と「ア」を同時に!
4. 子音
日本人が最も苦手とする子音TOP5
1. RとLの違い
💡 Right(正しい)
- 発音: 「ゥライッ」
- 口の形: 口を少しすぼめる(口笛の入り口)
- 舌の位置: 舌はどこにも触れず、少し奥に引っ込める
- 音の出し方: 喉の奥で「る」と響かせるように
💡 Light(光)
- 発音: 「ライッ」
- 口の形: 口元はあまりすぼめず、自然な形
- 舌の位置: 舌先を軽く上の前歯の裏にタッチ
- 音の出し方: 一瞬だけ触れて「ラ」とはじくように
🔥 聞き比べのコツ: Right →「口笛+ウ → ラ」 Light →「日本語の”ら”に近い → ラ」
2. [f]と[v]の違い(例:fan / van)
💡 Fan(扇風機)
- 発音: 「ファン」(日本語と近い)
- 口の形: 上の前歯で下唇を軽く噛む
- 音の出し方: 息だけ出す。声帯は震わせない(無声)
- 特徴: スーッと息が出る感覚
💡 Van(バン/車)
- 発音: 「ヴァン」
- 口の形: 同じく軽く噛む
- 音の出し方: 声を乗せる(有声)
- 特徴: 下唇がブブッと震える感覚があると◎
🔥 区別のコツ: 「V」はぶるぶる震える、「F」はスーッと息だけ
3. [θ]と[ð]の違い(例:think / this)
💡 Think(考える)
- 発音: 「スィンク」ではない!「ス」じゃなく「スとサの中間」
- 舌の位置: 舌先を上下の歯の間に出す(軽く挟む)
- 音の出し方: 息だけスーッと出す(無声)
- コツ: 歯と舌のスキマを意識
💡 This(これ)
- 発音: 「ズィス」ではない、「ズとザの中間」
- 舌の位置: 同じ舌の位置
- 音の出し方: 息に声を乗せる(有声)
- コツ: 舌を震わせる感覚
🔥 発音のコツ: 舌を出す勇気!恥ずかしがらずに「ベロ出し発音」
4. [p]と[b]のアスピレーション(息の強さ)
💡 Pin(ピン)
- 発音: 「ピン」+強い息
- 口の形: 唇を閉じて一気に開く
- 息の強さ: 「ピッ」という強い息が出る
- テスト方法: 手のひらに息を感じるくらい
💡 Bin(ゴミ箱)
- 発音: 「ビン」息は弱め
- 口の形: 同じく唇を閉じて開く
- 息の強さ: 息より声を重視
- 特徴: 下唇が軽く震える感覚
🔥 テスト方法: 手のひらを口元に当てて「Pin」→強い息、「Bin」→弱い息
5. [t]と[d]のアメリカ英語的フラッピング(例:water / better)
💡 Water(水)
- 発音: 「ウォーラー」(「ラ」に近い音)
- 音の特徴: [t]と[d]の間にある、ラ行っぽい「軽い舌打ち音」
- 舌の動き: 舌を一瞬だけ、どこかに触れそうで触れない
- 注意点: 日本語の「ラ」とは違う、弾くような音
💡 Better(より良い)
- 発音: 「ベラー」
- 音の特徴: 同じく軽い舌打ち音
- 舌の動き: 舌を歯茎に軽く弾ませる
- 特徴: 「ト」「ド」より「ル」に近い
🔥 フラッピング感覚: Get it = 「ゲリッ(ラ行っぽく)」 City = 「シリー」
5. 音声変化
🔗 リンキング(音の連結)
単語同士がつながって発音される現象
具体例:
- turn on → turnon(ターノン)
- an apple → anapple(アナップル)
- check it out → checkitout(チェキタウト)
- look at → lookat(ルカッ)
- come on → comon(カモン)
💪 弱系・強系
機能語(前置詞、助動詞、冠詞など)は通常「弱系」で発音される
例:
can(できる)
- 強系: /kæn/「できる」を強調
- 弱系: /kən/「普通の会話での”できる”」
to(〜へ)
- 強系: /tuː/「〜へ」を強調
- 弱系: /tə/「普通の会話での”〜へ”」
and(そして)
- 強系: /ænd/「そして」を強調
- 弱系: /ən/「普通の会話での”そして”」
✂️ 音の省略
子音クラスター簡略化
- asked → /æskt/ が /æst/ に
- friends → /frendz/ が /frenz/ に
- tests → /tests/ が /tess/ に
語末の /t/ /d/ 脱落
- last night → las’ night
- good morning → goo’ morning
- first time → firs’ time
弱い音の省略
- probably → prob’ly
- comfortable → comf’table
- vegetable → veg’table
6. イントネーションと意味
📈 基本的なイントネーションパターン
📉 下降調(↘)
用途: 平叙文、WH疑問文、命令文
例:
- I’m going home. ↘(家に帰ります)
- What time is it? ↘(何時ですか?)
- Close the door. ↘(ドアを閉めてください)
- That’s interesting. ↘(それは面白いですね)
📈 上昇調(↗)
用途: Yes/No疑問文、確認、驚き
例:
- Are you coming? ↗(来るんですか?)
- Really? ↗(本当に?)
- You’re leaving? ↗(帰るんですか?)
- Tomorrow? ↗(明日?)
📈📉 上昇-下降調(↗↘)
用途: 選択疑問文、リスト、対比
例:
- Do you want tea ↗ or coffee? ↘
- First, ↗ second, ↗ and finally ↘
- On the one hand ↗ but on the other hand ↘
💭 感情とイントネーション
😊 喜び・興奮:高い音調+幅広い音域
- That’s fantastic! ↗↘(それは素晴らしい!)
- I can’t believe it! ↗↘(信じられない!)
- Amazing! ↗↘(すごい!)
😔 悲しみ・失望:低い音調+狭い音域
- I’m so disappointed. ↘(とてもがっかりです)
- That’s too bad. ↘(それは残念です)
- I’m sorry to hear that. ↘(それは気の毒です)
😠 怒り・不満:強いストレス+急激な音調変化
- I can’t believe it! ↗↘(信じられない!)
- That’s ridiculous! ↗↘(ばかげている!)
- Stop it! ↗↘(やめて!)
🤔 疑問・困惑:上昇調+語尾延ばし
- What do you mean? ↗(どういう意味ですか?)
- I don’t understand. ↗(わかりません)
- Are you sure? ↗(本当ですか?)
🎯 焦点とイントネーション
文中の最も重要な語を高く、強く発音
例:
- I bought a RED car. (赤い車を買いました – 色が重要)
- I BOUGHT a red car. (赤い車を買いました – 購入行為が重要)
- I bought a red CAR. (赤い車を買いました – 車であることが重要)
応用例:
- JOHN called yesterday. (ジョンが昨日電話した – 誰が重要)
- John CALLED yesterday. (ジョンが昨日電話した – 行為が重要)
- John called YESTERDAY. (ジョンが昨日電話した – いつが重要)
🎯 効果的な練習方法
1. 🪞 鏡を使った口の形チェック
- 各音を発音するときの口と舌の形を確認
- 特に[θ][ð]は舌を出す勇気が必要!
- 母音の口の開き具合をチェック
2. 🎤 録音して聞き比べ
- 自分の発音を録音
- ネイティブの発音と比較
- 違いを客観的に分析
- 定期的に録音して上達を確認
3. 🎵 ミニマル・ペア練習
- 似た音の単語を交互に発音
- 例:Right – Light – Right – Light…
- 例:Ship – Sheep – Ship – Sheep…
- 例:Sit – Seat – Sit – Seat…
4. 🎭 シャドーイング
- ネイティブの音声に0.5秒遅れでついていく
- 音の変化やリズムを体で覚える
- 最初は遅めの音声から始める
- 徐々に自然なスピードに慣れる
5. 🔤 IPA表記を活用した練習
- 辞書のIPA表記を必ず確認
- 音と記号の対応を覚える
- 自分で音を記号に変換する練習
- IPA表を見ながら発音練習
💡 まとめ:発音上達のコツ
🎯 基本的な心構え
- 完璧を目指さない:70%できれば十分通じる
- 一つずつ集中:全部同時ではなく、一つの音をマスターしてから次へ
- 毎日少しずつ:10分でも継続が大切
- 恥ずかしがらない:大げさな口の動きが正解
- 聞き取りから始める:発音できない音は聞き取れない
🔧 技術的なポイント
- IPA表記を活用:正確な音の理解には不可欠
- 音声変化を意識:実際の会話での音の変化を理解する
- イントネーションで意味を表現:単語の発音だけでなく、文全体の音調変化も重要
- リズムを重視:英語のストレス・タイミングを身につける
- 録音による客観的チェック:自分の発音を客観的に分析
発音は一朝一夕では身につきませんが、正しい方法で継続すれば必ず上達します。今日から一つの音でも意識して、世界に通じる英語を目指しましょう!
🎧 発音練習におすすめのツール
📱 アプリ・オンラインツール
- Forvo(ネイティブ発音辞書)
- ELSA Speak(AI発音矯正アプリ)
- Youglish(YouTube発音検索)
- Sounds Pronunciation(BBC Learning English)
📚 辞書・参考書
- Cambridge Dictionary(IPA表記あり)
- Longman Dictionary(発音記号付き)
- Oxford Dictionary(音声付き)
- IPA Chart(国際音声記号一覧)
🎬 学習コンテンツ
- TED Talks(字幕付きでシャドーイング)
- BBC Learning English(発音コーナー)
- Rachel’s English(YouTube発音チャンネル)
- Pronunciation Studio(イギリス英語発音)
📌 最後に この記事を参考に、毎日少しずつでも発音練習を続けてください。完璧を目指さず、着実に一歩ずつ上達していけば、必ず世界に通じる英語発音が身につきます!
🌟 頑張って練習を続けましょう!
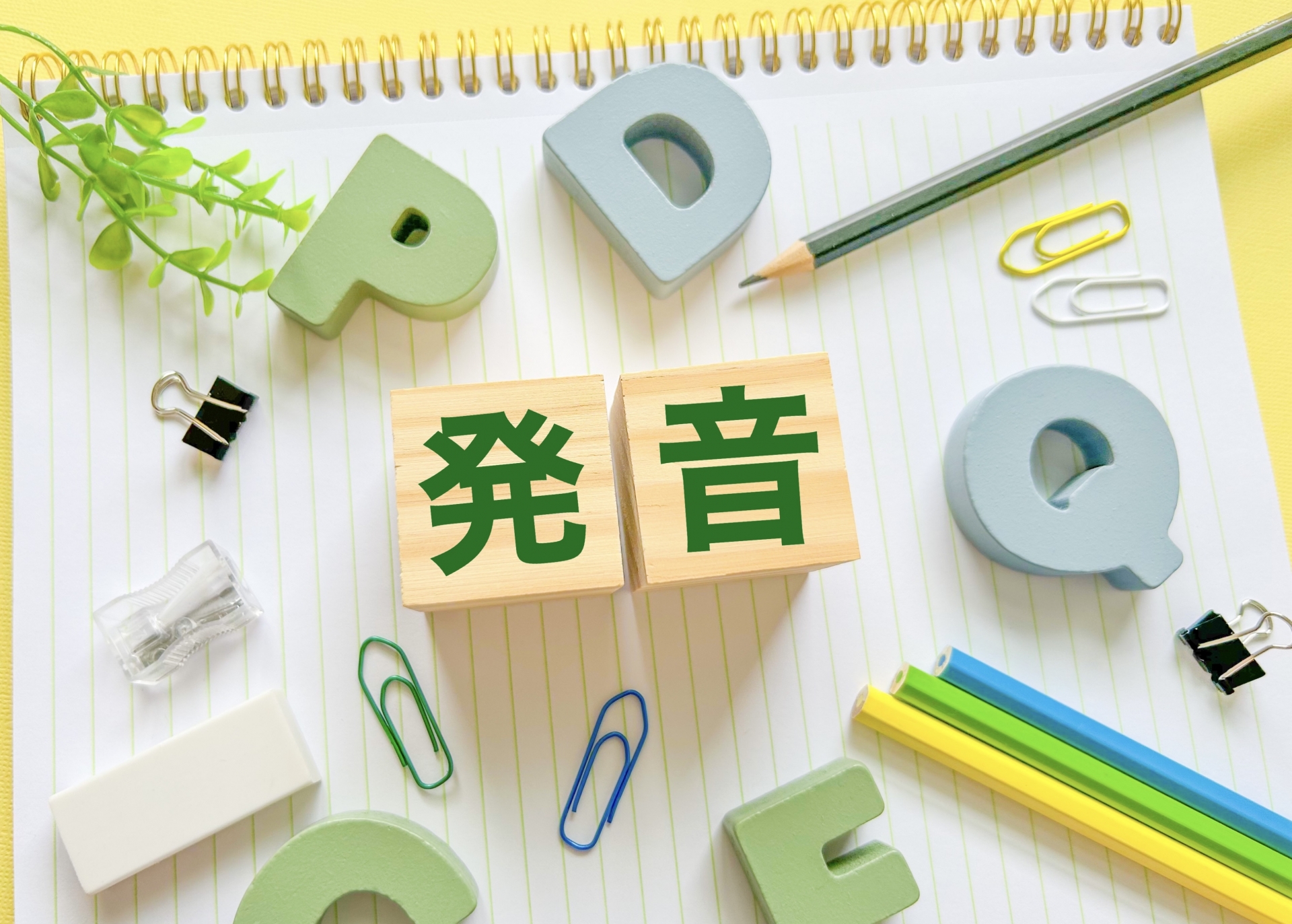









コメント